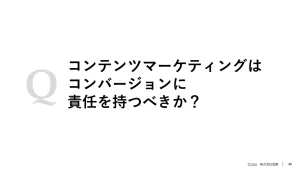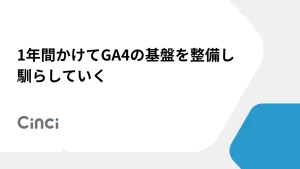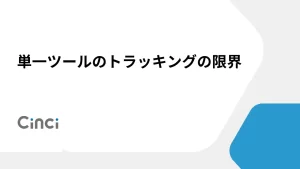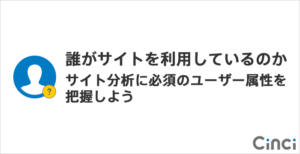ダイレクトなトラフィックは、もうご指名流入ではなくダークトラフィックだ

「直接アクセス」「ノーリファラー」などとも呼ばれる「ダイレクトトラフィック」。昔から定義そのものは変わっておらず、「リファラー情報を取得できないサイト流入」を意味します。
ダイレクトトラフィックは、以前であれば「ご指名系の流入」「リピーター層」と捉える風潮もありました。「ブラウザーブックマーク経由流入」「URLの直接入力やオートコンプリートでの流入」が一定数含まれるためです。
しかし、もう近年はそのような「エンゲージメントがきっと高い流入」ばかりではなくなりました。リファラー情報を取得できないトラフィックは多様化し、当初からの定義のとおり「どこから来たのかが不明」なものが増加しています。やっかいなのは、どれだけの量と種類が増えたのかがわからないということです。
このような「リファラーが不明な流入」は「ダークトラフィック」とも呼ばれます。ネガティブな意味はありません。これまで一方的に重要さを背負わせていた状態ではなくなった、と言えます。文字通り「どこからやってきたかわからない流入」です。
主要なダイレクトトラフィック
主要なものを改めて挙げてみます。一般的な事象として挙げているため個別の例外はあります。
- ブラウザーブックマーク経由、履歴経由
- URL直接入力、オートコンプリート
- メールソフトやローカルアプリケーション経由、スマートフォンアプリ経由
- チャットやメッセンジャー経由
- QRコード経由
- Google Discover経由
- rel属性に「noreferrer」が付与されたaタグのリンク経由
- リファラー送信拒否(ブラウザーアドオン、セキュリティソフト)
- httpsからhttpへのリンク経由
- 一部のJavaScriptリダイレクト、meta refreshリダイレクト
3)のアプリ経由、4)のチャット、7)のnoreferrerリンクなどが増加しているのではないでしょうか。
例えば、LINE経由の流入はいまでもリファラーを持っていません。Slackはデフォルトでリファラーを外す設定になっています。Zoomのチャットもリファラーはありません。BtoBの顧客層にてSlackなどによる社内共有コミュニケーションが活発であれば、ダイレクトトラフィックは増えるでしょう。
「rel属性に『noreferrer』が付与されたリンク」も増加しました。例えばWordPressの普及したエディターの中には、デフォルトでリンクのrel属性にnoopenerとnoreferrerを付与するものがあります(皆さんのオウンドメディアをチェックしてみてください)。利用者の多いコンテンツ配信サイト「note」も、別ウインドウで開くリンクにはnoreferrerが付与されるものがあります(そうではないものもあります)。

Google Discover経由の流入も、アクセス解析で参照元を判別できません。
ダイレクトトラフィックの内訳はわからない
正直なところ、ダイレクトトラフィックの内訳やどれがどれだけ増減したのかなどはわかりません。ただ、「ご指名流入以外」のトラフィックはおそらく増えています。ソーシャルメディアでサイト内のページが話題になると、そのページへのダイレクトトラフィックも増加することに気付いている担当者も多いはずです。
ダイレクトトラフィックに対して何か特別な施策を行うケースは少ないように思いますが、従来のようなステレオタイプな見方は避けるべきでしょう。依然として重要なトラフィックを多く含みますが、もしそこにフォーカスを当てるのであれば、それが何なのかを類推しなければいけません。
コントロールできる流入チャネルではパラメータ付与で回避
当然ながら、自社がコントロールできる流入チャネルでは、リンク先URLにパラメータを付与することでダークトラフィックな状況を少し回避できます。例えばGoogleアナリティクスのUTMパラメータを利用すれば参照元を判別できます。メルマガやLINE、QRコードなどが該当します。
なお、TwitterやFacebook、Instagramなどはアプリ経由流入であっても基本的にはリファラーが付与されています(ただし例外もありそうです)。
GAの活用体制づくり、ダッシュボード構築、既存の計測設定の見直しなどをサポートします。